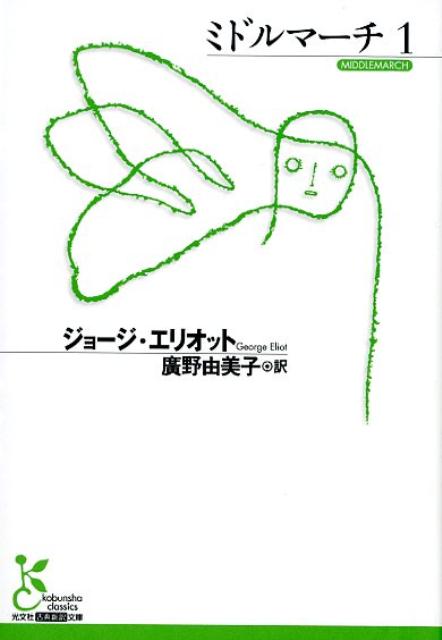ジョージ・エリオット(George Eliot)
1819年11月22日〜1880年12月22日(61歳)
イングランド、ウォリックシャー州ヌニートン出身。
国籍=イギリス。
小説家。
代表作は『ミドルマーチ』『サイラス・マーナー』『アダム・ビード』など。
男性名のペンネームを用いたイギリスの女性作家。
名言=「微笑めば友達ができる。しかめっ面をすればしわができる。」

『ジョージ・エリオット』の名言・格言
心の迷いを消してくれる。
数々の名言を連発しているジョージ・エリオットさん。
その中でも『ジョージ・エリオット』の名言をご紹介していきます。
成長の最大の源は選択にある。
寛容であることは、広い視野を持っている人々の義務である。
残虐行為は他のすべての悪事と同様に、外的な動機を必要としない。
機会を必要とするだけだ。
もちろん男性は何でも最もよく知っています。
女性の方がもっとよく知っているということを除いてね。
臆病者は勝つと分かっている戦いしかできない。
だがどうか、負けると知りつつも戦える勇気を。
時に勝利よりも価値ある敗北というのもあるのだから。
過ちを非難しすぎるよりも、過ちを許しすぎる方がずっといい。
さあ顔を上げて!
君は失敗するために生まれてきたんじゃない、成功するために生まれてきたんだ。
嬉々とした自信を持って前に進め。
微笑めば友達ができる。
しかめっ面をすればしわができる。
バラが空から降ってくることはない。
もっとバラが欲しければ、もっと多くの木を植えなさい。
確かさばかり求めてぐずぐずしている人には、大きなことは決してできない。
自分の仕事が最高と思えたら、成功です。
なりたかった自分になるのに遅すぎるということはない。
冒険とは外の世界にあるのではなく、心の中にある。
わたしは過去との結び付きを壊すような未来を望まない。
前向きな態度
- それは生きるための目的ではなく、手段である。
人にお世辞を言われた時、いい気になって嬉しそうな顔をする者は傲慢な人である。
他人の悪口を聞いて喜ぶ者は心のいやしい人である。
愛されるだけでは物足りない。
愛の言葉もかけてほしい。
静寂の世界は、お墓の中で十分に味わえるのだから。
彼は、自分の鳴き声を聴くために太陽は昇ると思っている鶏のような人だ。
さまざまな観点から対象を見ることができないのは心が狭いということです。
機会を利用できない者にとって、「機会」とは時の波が虚無の海へ流し去る、決して孵化しない卵である。
私たちが行動を決定するように、行動も私たちの人間性を決めている。
人生を退屈なものにするのは動機の欠如である。
結婚とは、同情か征服かのいずれかの関係である。
冗談の好みの違いは、愛情にとって大きな負担だ。
私は女性が愚か者であるということを否定はいたしませんが、全能の神は男性につりあうように女性を作られたのです。
信用されないほど寂しいことがあるだろうか。
動物ほど気持ちのよい友達はいない。
彼らは質問もしなければ批判もしない。
別れの激しい苦痛によってのみ、愛の深みを見ることができるのだ。
最も幸福な女性は、最も幸福な国と同じように、歴史を持っていない。
空の星になれないなら、せめて家庭の灯になりなさい。
詩とは、感情の解放ではなくて感情からの脱出であり、人格の表現ではなく人格からの脱出である。
自分のためだけに心の狭い楽しみを、ひたすら追い求めた結果訪れる幸福は、次元の低い幸福だけである。
広い考え方を持ち、自分ばかりでなく、世の中の他の人々にも関心を示してはじめて、大いなるものと歩調を共にするような、次元の高い幸福を手にすることができる。
婦人の運命はその愛される分量の如何にある。
ゴシップはパイプやたばこがまき散らす一種の煙で、スモーカーの悪趣味以外の何ものでもない。
言葉は翼を持つが、思うところに飛ばない。
お互いの人生をもっと楽にするためでないのなら、私たちはなんのために生きているのでしょうか?
何も言うべきことがないときに、それを口で証明するのでなく慎んでいてくれる人というのは、ありがたいものです。
私たちが成し遂げたものは、遠く離れて私たちのあとをついてきている。
何を成し遂げたかで、私たちという人間が決まるのだ。
性格とは、固くもなければ不変でもない。
活動し、変化し、肉体と同じように病気にもなるのだ。
無知は大きな可能性の枠を与える。
人生の流れの中で、輝かしい瞬間はあっという間に過ぎ去り、今は砂原しか見えない。
天使が私たちを尋ねてくる。
だけどそのことに気が付くのは、彼らが去ってしまったあとのこと。
人生は、目を覚まして母の顔を愛するところから始まった。
悪魔が私たちを誘惑するのではない。
私たちが悪魔を誘惑するのだ。
盗んだ蜜を味わったからには、金で無実を買うわけにはいかない。
何事も実現するまでが一番楽しい。
死者も我々がまったく忘れてしまうまで、本当に死んだのではない。