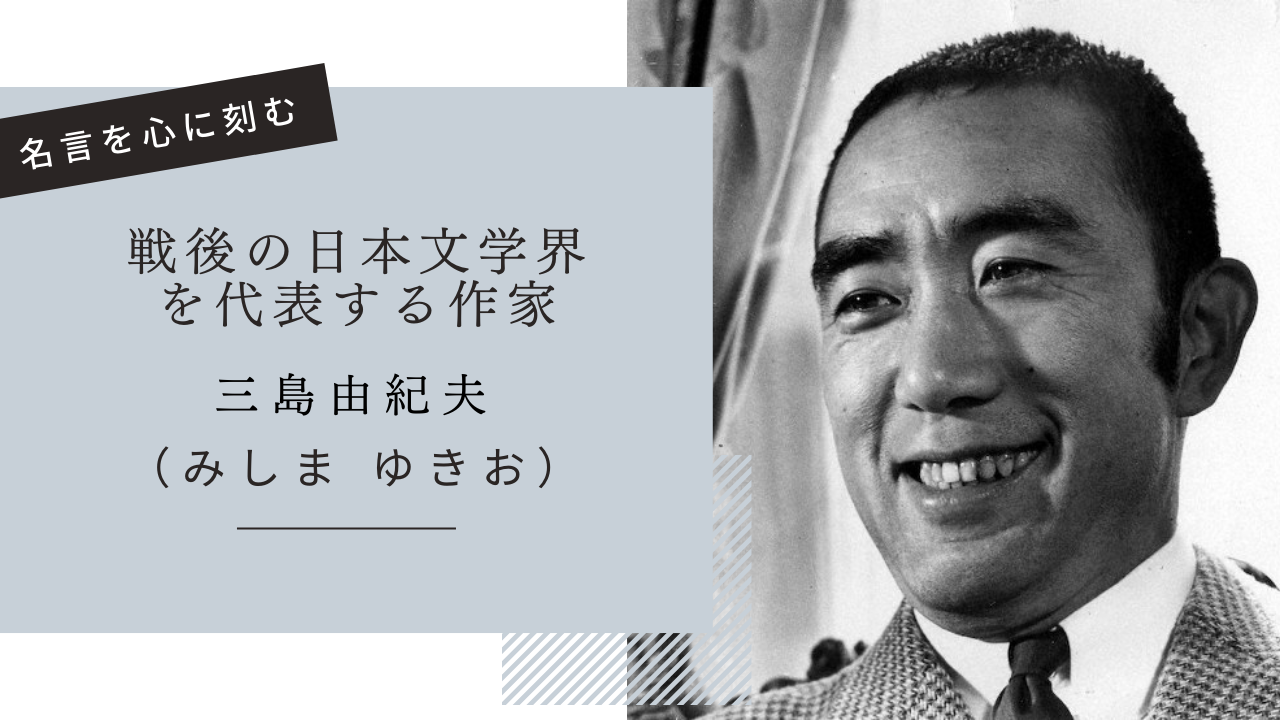三島由紀夫(みしま ゆきお)
1925年1月14日〜1970年11月25日(45歳)
東京市四谷区永住町(現在の新宿区四谷四丁目)出身。
国籍=日本。
小説家、劇作家、随筆家、評論家、政治活動家。
代表作は『仮面の告白』『潮騒』『金閣寺』など。戦後の日本文学界を代表する作家の一人であり、「三島事件」により日本社会に大きな衝撃をもたらした。
名言=「傷つきやすい人間ほど、複雑な鎧帷子(よろいかたびら)を身につけるものだ。そして往々この鎧帷子が、自分の肌を傷つけてしまう。」

『三島由紀夫』の名言・格言
心の迷いを消してくれる。
数々の名言を連発している三島由紀夫さん。
その中でも『三島由紀夫』の名言をご紹介していきます。
そもそも男の人生にとって大きな悲劇は、女性というものを誤解することである。
現状維持というのは、つねに醜悪な思想であり、また、現状破壊というのは、つねに飢え渇いた貧しい思想である。
鈍感な人たちは、血が流れなければ狼狽しない。
が、血の流れたときは、悲劇は終わってしまったあとなのである。
傷つきやすい人間ほど、複雑な鎧帷子(よろいかたびら)を身につけるものだ。
そして往々この鎧帷子が、自分の肌を傷つけてしまう。
人間はあやまちを犯してはじめて真理を知る。
軽蔑とは、女の男に対する永遠の批評である。
日本という国は、自発的な革命はやらない国である。
革命の惨禍が避けがたいものならば、自分で手を下すより、外力のせいにしたほうがよい。
空虚な目標であれ、目標をめざして努力する過程にしか人間の幸福は存在しない。
人間に忘却と、それに伴う過去の美化がなかったら、人間はどうして生に耐えることができるだろう。
アイデンティティーとは指紋である。
最終的に一つあればいいんだ。
初恋に勝って人生に失敗するというのは良くある例で、初恋は破れるほうがいいと言う説もある。
夕日とか菫の花とか風鈴とか美しい小鳥とか、そういう凡庸な美に対する飽くことのない傾倒が、女性を真に魅力あるものにするのである。
本当の美とは人を黙らせるものであります。
若さが幸福を求めるなどというのは衰退である。
忘却の早さと、何事も重大視しない情感の浅さこそ人間の最初の老いの兆しだ。
復興には時間がかかる。
ところが、復興という奴が、又日本人の十八番なのである。
どうも日本人は、改革の情熱よりも、復興の情熱に適しているところがある。
人間、正道を歩むのはかえって不安なものだ。
「・・・したい」などという心はみな捨てる。
その代わりに、「・・・すべきだ」ということを自分の基本原理にする。
そうだ、ほんとうにそうすべきだ。
この世のもっとも純粋な喜びは、他人の喜びをみることだ。
なぜ大人は酒を飲むのか。
大人になると悲しいことに、酒を呑まなくては酔へないからである。
子供なら、何も呑まなくても、忽ち遊びに酔つてしまふことができる。
愛するということにかけては、女性こそ専門家で、男性は永遠の素人である。
感傷といふものが女性的な特質のやうに考へられてゐるのは明らかに誤解である。
感傷的といふことは男性的といふことなのだ。
幸福がつかの間だという哲学は、不幸な人間も、幸福な人間も、どちらも好い気持ちにさせる力を持っている。
時の流れは、崇高なものを、なしくずしに、滑稽なものに変えてゆく。
若い世代は、代々、その特有な時代病を看板にして次々と登場して来たのだった。
女性はそもそも、いろんな点でお月さまに似てをり、お月さまの影響を受けてゐるが、男に比して、すぐ肥つたりすぐやせたりしやすいところもお月さまそつくりである。
小説家のほうが読者より人生をよく知っていて、人に道標を与えることができる、などというのも完全な迷信です。
小説家自身が人生にアップアップしているのであって、それから木片につかまって、一息ついている姿が、すなわち彼の小説を書いている姿です。
人生には濃い薄い、多い少ない、ということはありません。
誰にも一ぺんコッキリの人生しかないのです。
生命尊重のみで、魂は死んでもよいのか。
青春の特権といえば、一言を以てすれば、無知の特権であろう。
男の嫉妬の本当のギリギリのところは、体面を傷つけられた怒りだと断言してもよろしい。
賭けとは全身全霊の行為である。
百万円持っていた人間が、百万円を賭け切るときにしか、賭けの真価はあらわれない。
変わり者と理想家とは、一つの貨幣の両面であることが多い。
どちらも、説明のつかないものに対して、第三者からはどう見ても無意味なものに対して、頑固に忠実にありつづける。
無秩序が文学に愛されるのは、文学そのものが秩序の化身だからだ。
老夫妻の間の友情のようなものは、友情のもっとも美しい芸術品である。
エチケットなどというものは、俗の俗なるもので、その人の偉さとは何の関係もないのである。
センスとは相手の気持ちを読みとること、ただそれのみだ。
ヒットラーは政治的天才であつたが、英雄ではなかつた。
英雄といふものに必要な、爽やかさ、晴れやかさが、彼には徹底的に欠けてゐた。
ヒットラーは、二十世紀そのもののやうに暗い。
音楽の美は、その一瞬の短さにおいて生命に似ている。
個性などというものは、はじめは醜い、ぶざまな恰好をしているものだ。
幸福って、何も感じないことよ。
幸福って、もっと鈍感なものよ。
・・・幸福な人は、自分以外のことなんか夢にも考えないで生きてゆくんですよ。
自分の顔と折合いをつけながら、だんだんに年をとってゆくのは賢明な方法である。
女というものは、いたわられるのは大好きなくせに、顔色を窺われるのはきらうものだ。
いつでも、的確に、しかもムンズとばかりにいたわってほしいのである。
女性は先天的に愛の天才である。
どんなに愚かな身勝手な愛し方をする女でも、そこには何か有無を言わせぬ力がある。
親しくなればなるほど礼節をわきまえるのが理想の人間関係である。
崇高なものが現代では無力で、滑稽なものにだけ野蛮な力がある。
精神を凌駕することのできるのは習慣という怪物だけなのだ。
先生にあわれみをもつがよろしい。
薄給の教師に、あわれみをもつのがよろしい。
先生という種族は、諸君の逢うあらゆる大人のなかで、一等手強くない大人なのです。
男の世界は思いやりの世界である。
男の社会的な能力とは思いやりの能力である。
武士道の世界は、一見荒々しい世界のように見えながら、現代よりももっと緻密な人間同士の思いやりのうえに、精密に運営されていた。
動物になるべき時には、ちゃんと動物になれない人間は不潔であります。
僕は詩人の顔と闘牛師の体とを持ちたい。
裏切りは友情の薬味であって、コショウかワサビみたいなものであり、裏切りの要素もその危険も伏在しない友情など、味がないと思うようになるとき、諸君はまず、青年のセンチメンタリズムを脱却した、一人前の大人になったと云えましょう。
この世には最高の瞬間といふものがある。
この世における精神と自然との和解、精神と自然との交合の瞬間だ。
たいてい勇気ある行動というものは、別の在るものへの怖れから来ているもので、全然恐怖心のない人には、勇気の生まれる余地がなくて、そういう人はただ無茶をやってのけるだけの話です。
やたらに人に弱味をさらけ出す人間のことを私は躊躇なく「無礼者」と呼びます。
それは社会的無礼であって、われわれは自分の弱さをいやがる気持ちから人の長所をみとめるのに、人も同じように弱いということを証明してくれるのは、無礼千万なのであります。
何か、極く小さな、どんなありきたりな希望でもよい。
それがなくては、人は明日のはうへ生き延びることができない。
好奇心には道徳がないのである。
もしかするとそれは人間のもちうるもつとも不徳な欲望かもしれない。
三千人と恋愛をした人が、一人と恋愛をした人に比べて、より多くについて知っているとはいえないのが、人生の面白味です。
自分を理解しない人間を寄せつけないのは、芸術家として正しい態度である。
芸術家は政治家じゃないのだから。
女の部屋は一度ノックすべきである。
しかし二度ノックすべきじゃない。
そうするくらいなら、むしろノックせずに、いきなりドアをあけたはうが上策なのである。
小説家にとっては今日書く一行が、テメエの全身的表現だ。
明日の朝、自分は死ぬかもしれない。
その覚悟なくして、どうして今日書く一行に力がこもるかね。
その一行に、自分の中の集合的無意識に連綿と続いてきた“文化”が、体を通して現れ、定着する。
その一行に自分が“成就”する。
それが“創造”というものの、本当の意味だよ。
未来のための創造なんて、絶対に嘘だ。
人間を一番残酷にするのは 愛されているという自信だよ。
生まれて来て何を最初に教わるって、それは「諦める」ことよ。
精神分析を待つまでもなく、人間のつく嘘のうちで、「一度も嘘をついたことがない」といふのは、おそらく最大の嘘である。
男と女の一等厄介なちがいは、男にとっては精神と肉体がはっきり区別して意識されているのに、女にとっては精神と肉体がどこまで行ってもまざり合っていることである。
男性操縦の最高の秘訣は、男のセンチメンタリズムをギュッとにぎることだ。
美しい若い女が、大金持の老人の恋人になっているとき、人は打算的な愛だと推測したがるが、それはまちがっている。
打算をとおしてさえ、愛の専門家は愛を紡ぎ出すことができるのだ。
無神論も、徹底すれば徹底するほど、唯一神信仰の裏返しにすぎぬ。
無気力も、徹底すれば徹底するほど、情熱の裏返しにすぎぬ。
力を持たない知性なんて、屁の役にも立たない。
あらゆる文章は形容詞から古くなっていく。