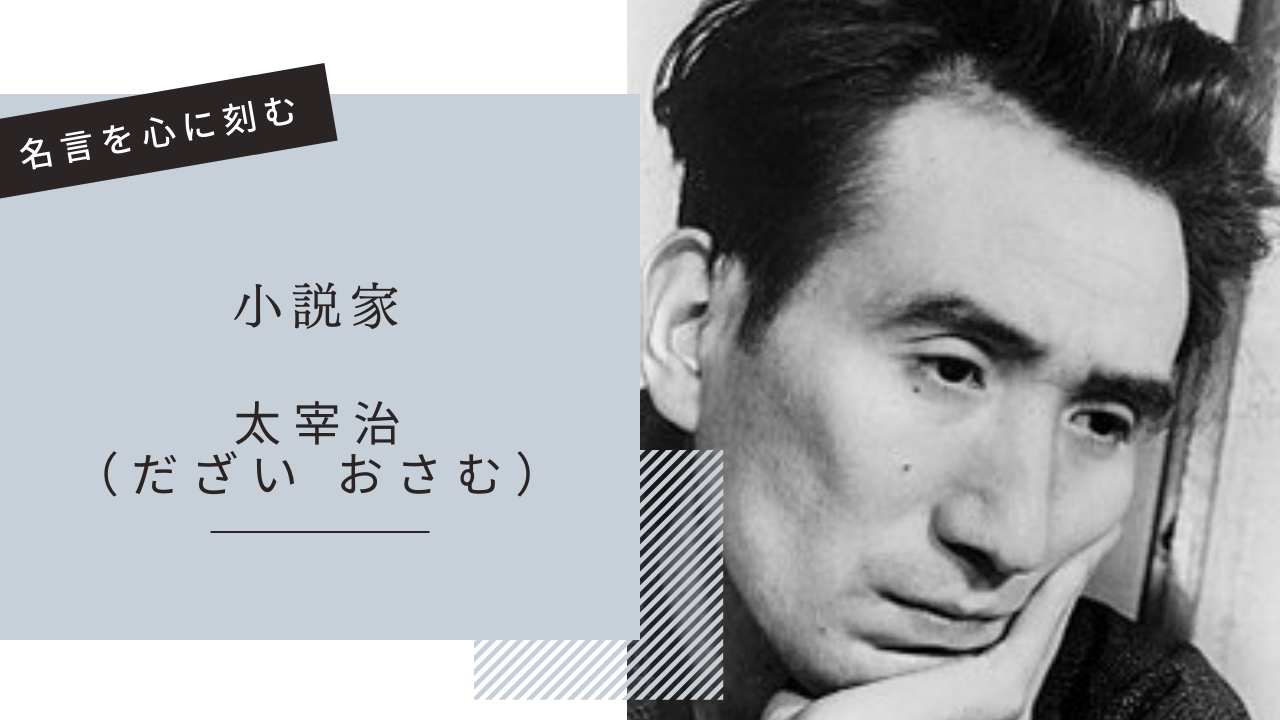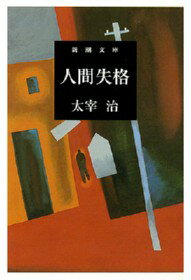太宰治(だざい おさむ)
1909年6月19日〜1948年6月13日(38歳)
青森県北津軽郡金木村(現在の五所川原市)出身。
国籍=日本。
小説家。
代表作は『走れメロス』『お伽草紙』『斜陽』『人間失格』など。
名言=「笑われて、笑われて、つよくなる。」
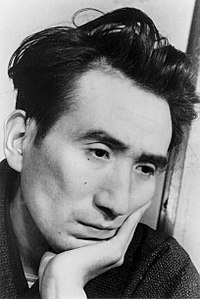
『太宰治』の名言・格言
心の迷いを消してくれる。
数々の名言を連発している太宰治さん。
その中でも『太宰治』の名言をご紹介していきます。
人間は、しばしば希望にあざむかれるが、しかし、また、「絶望」という観念にも同様にあざむかれる事がある。
人間のプライドの究極の立脚点は、あれにも、これにも死ぬほど苦しんだ事があります、と言い切れる自覚ではないか。
一日一日を、たっぷりと生きて行くより他は無い。
明日のことを思い煩うな。
明日は明日みずから思い煩わん。
きょう一日を、よろこび、努め、人には優しくして暮したい。
私はなんにも知りません。
しかし、伸びて行く方向に陽が当たるようです。
私は、ひとの恋愛談を聞く事は、あまり好きでない。
恋愛談には、かならず、どこかに言い繕いがあるからである。
疑いながら、ためしに右へ曲るのも、信じて断乎として右へ曲るのも、その運命は同じ事です。
どっちにしたって引き返すことは出来ないんだ。
人間三百六十五日、何の心配も無い日が、一日、いや半日あったら、それは仕合せな人間です。
あなたはさっきから、乙姫の居所を前方にばかり求めていらっしゃる。
ここにあなたの重大なる誤謬が存在していたわけだ。
なぜ、あなたは頭上を見ないのです。
また、脚下を見ないのです。
恋愛は、チャンスではないと思う。
私はそれを意志だと思う。
君のような秀才にはわかるまいが、「自分の生きていることが、人に迷惑をかける。僕は余計者だ」という意識ほどつらい思いは世の中に無い。
幸福の便りというものは、待っている時には決して来ないものだ。
弱虫は、幸福をさえおそれるものです。
綿で怪我するんです。
幸福に傷つけられる事もあるんです。
怒涛に飛び込む思いで愛の言葉を叫ぶところに、愛の実体があるのだ。
学問なんて、覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだ。
けれども、全部忘れてしまっても、その勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残っているものだ。
これだ。
これが貴いのだ。
勉強しなければいかん。
笑われて、笑われて、つよくなる。
好奇心を爆発させるのも冒険、また、好奇心を抑制するのも、やっぱり冒険、どちらも危険さ。
人には、宿命というものがあるんだよ。
信じられているから走るのだ。
間に合う、間に合わぬは問題でないのだ。
人間の生活の苦しみは、愛の表現の困難に尽きるといってよいと思う。
この表現のつたなさが、人間の不幸の源泉なのではあるまいか。
怒る時に怒らなければ、人間の甲斐がありません。
愛することは、いのちがけだよ。
甘いとは思わない。
てれくさくて言えないというのは、つまりは自分を大事にしているからだ。
駄目な男というものは、幸福を受け取るに当たってさえ、下手くそを極めるものである。
安楽なくらしをしているときは、絶望の詩を作り、ひしがれたくらしをしているときは生のよろこびを書きつづる。
信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。
人から尊敬されようと思わぬ人たちと遊びたい。
けれども、そんないい人たちは、僕と遊んでくれやしない。
男って、正直ね。
何もかも、まる見えなのに、それでも、何かと女をだました気で居るらしいのね。
犬は、爪を隠せないのね。
僕は自分がなぜ生きていなければならないのか、それが全然わからないのです。
ぽかんと花を眺めながら、人間も、本当によいところがある、と思った。
花の美しさを見つけたのは人間だし、花を愛するのも人間だもの。
理窟はないんだ。
女の好ききらいなんて、ずいぶんいい加減なものだと思う。
今の女性は個性がない、深みがない、
批判はあっても答えがない、独創性に乏しく模倣ばかり。
さらに無責任で自重を知らず、お上品ぶっていながら気品がない。
本当の気品というものは、真黒いどっしりした大きい岩に白菊一輪だ。
不良とは、優しさの事ではないかしら。
大人とは、裏切られた青年の姿である。
僕は今まで、説教されて、改心したことが、まだいちどもない。
説教している人を、偉いなあと思ったことも、まだ一度もない。
子供より親が大事、と思いたい。
子供のために、等と、古風な道学者みたいな事を殊勝さらく考えても、何、子供よりも、その親の方が弱いのだ。
親が無くても子は育つ、という。
私の場合、親が有るから子は育たぬのだ。
人は人に影響を与えることもできず、また人から影響を受けることもできない。
鉄は赤く熱しているうちに打つべきである。
花は満開のうちに眺むべきである。
私は晩年の芸術というものを否定している。
人間は不幸のどん底につき落とされ、ころげ廻りながらも、いつかしら一縷の希望の糸を手さぐりで捜し当てているものだ。