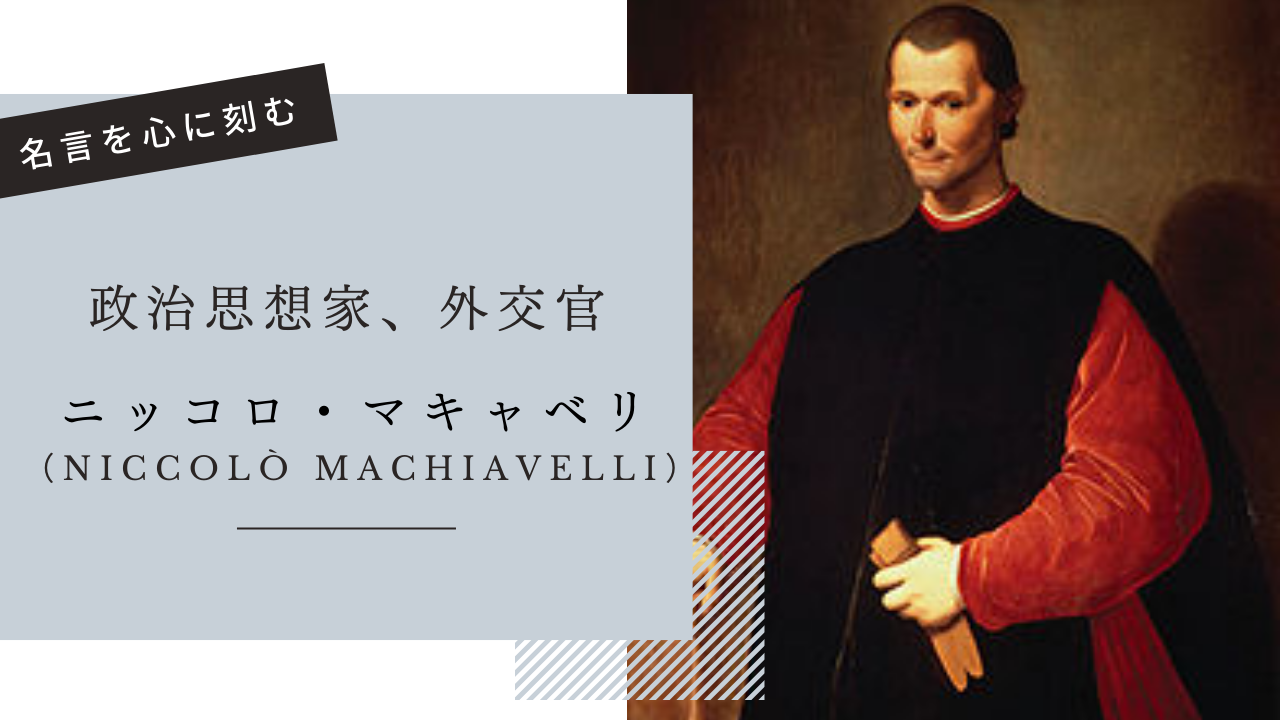ニッコロ・マキャベリ「マキャヴェリ」「マキャヴェッリ」ともいう(Niccolò Machiavelli)
1469年5月3日〜1527年6月21日(58歳)
フィレンツェ共和国フィレンツェ出身。
国籍=イタリア。
政治思想家、外交官。
代表作は『君主論』。理想主義的な思想の強いルネサンス期に、政治は宗教・道徳から切り離して考えるべきであるという現実主義的な政治理論を創始した。
名言=「人間は、恐れている人より、愛情をかけてくれる人を容赦なく傷付けるものである。」
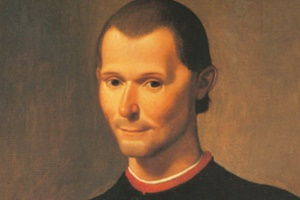
『マキャベリ』の名言・格言
心の迷いを消してくれる。
数々の名言を連発しているマキャベリさん。
その中でも『マキャベリ』の名言をご紹介していきます。
天気のいい日に嵐のことなど考えてもみないのは、人間共通の弱点である。
政治は道徳とは無縁である。
いかなる種類の闘いといえども、あなた自身の弱体化につながりそうな闘いは、絶対にしてはならない。
自らの安全を自らの力によって守る意思を持たない場合、いかなる国家といえども、独立と平和を期待することはできない。
決断力のない君主は、多くの場合、当面の危険を回避しようとして中立を選ぶ。
そしておおかたその君主は滅んでしまう。
敵の計略を見抜くことほど、指揮官にとって重要なことはない。
人間は誰でも自分のすることについて自負心を持っているものであり、それゆえにみずから欺かれやすいのだ。
民衆というものは、善政に浴している限り、特に自由などを望みもしなければ、求めもしないものである。
自らの武力を持っていなければ、どんな国でも安泰ではない。
自ら実力を持たない権力者の名声ほど、当てにならないものはない。
変革というものは、ひとつ起こると、必ずや次の変革を呼ぶようにできているものである。
私は断言しても良いが、中立を保つことは、あまり有効な選択ではないと思う。
人に危害を加えるときは、復讐をおそれる必要がないように痛烈にやらなければならない。
恩恵は、人々に長くそれを味わわせるためにも小出しに施すべきである。
新秩序の導入は、旧制度下で上手くやってきた者すべてを敵にまわすことになる。
人間は往々にして小鳥のような行動を取る。
小鳥は目の前の餌だけに注意を奪われ、鷹が頭上を飛んでいるのに気付かない。
大いなる意欲のあるところに、大いなる困難はない。
戦いを避けるために譲歩しても、結局は戦いを避けることは出来ない。
なぜなら譲歩しても相手は満足せず、譲歩するあなたに敬意を感じなくなり、より多くを奪おうと考えるからである。
議題が何であれ、進むべき方向と反対に議論は進み、本当に有益な意見を述べる者ではなく、うわべを取り繕った意見を述べる者が会議を支配する。
好機というものは、すぐさま捕まえないと逃げ去ってしまうものである。
他社を強力にする原因を作るものは、自滅する。
次の二つは絶対に軽視してはならない。
第一は、寛容と忍耐をもってしては、人間の敵意は決して溶解しない。
第二は、報酬と経済援助などの援助を与えても敵対関係は好転しない。
個人でも国家でも同じだが、相手を絶望と怒りに駆り立てるほど、痛めつけてはならない。
やむを得ないときの戦いは正しい。
武器の他に希望を絶たれたときには、武器もまた許されるものである。
太陽の下には、永遠なものは存在しない。
運命の女神はその変化を楽しもうとし、人間はそれによって彼女の力を明らかに知るのである。
敵に対する態度と味方に対する態度を、はっきり分けて示すことである。
民衆は無知ではあるが、真実を見抜く力はある。
君主たるものは、才能ある人材を登用し、その功績に対しては、十分に報いることも知らねばならない。
権力を持った人々の間でも、最近与えた恩恵によって以前の怨念が消えるなどと思う人がいたならば、その人は取り返しのつかない誤りを犯すことになる。
たとえ人の生命を奪っても、財布に手をかけてはならない。
人は父親を殺されたことは忘れても、遺産を失ったことは忘れないからだ。
肩書が人間を持ち上げるのではなく、人間が肩書を輝かせる。
運命は我々の行動の半分を支配し、残りの半分を我々自身にゆだねている。
決断に手間取ることは、これまた常に有害である。
人間は、恐れている人より、愛情をかけてくれる人を容赦なく傷付けるものである。
運命は材料を与えてくれるだけで、それをどう料理するかは自分しだいである。
祖国の存亡がかかっているような場合は、いかなる手段もその目的にとって有効ならば正当化される。
決断力に欠ける人々がいかにまじめに協議しようとも、そこから出てくる結論は常に曖昧で、それ故、常に役立たないものである。
また、優柔不断さに劣らず、長時間の討議の末の遅すぎる結論も同じく有害であることに変わりない。
敵と見られていた人々は、その評判を消したいという思いから、なお一層君主のために精を出すようになる。
愚者が最後にすることを、賢者は瞬時に行う。
中立の立場をとった場合、勝者にとっての敵となるばかりでなく、敗者からも助けてくれなかったという敵視を受けることとなる。
君主たる者、けちだという評判を恐れてはならない。
高慢な相手には、服従すれば勝てると考えるのは誤りである。
およそ人の頭脳には三通りある。
第一は自分で判断をつけるもの、第二は他人の考えがわかるもの。
第三は自分でも判らず、他人の考えも判らぬもの。
第一はもっとも優れ、第二も善く、第三は無能である。
どれほど困難が控えていようとも、表面的に得になりそうなら民衆を説得するのは難しくない。
反対に有益な政策でも、表面的に損になりそうな場合は民衆の賛同を得るのは大変困難である。
困難な時代には、真の力量を備えた人物が活躍するが、太平の世の中では、財の豊かな者や門閥に支えられた者が、わが世の春を謳歌することになる。
人間の意見なるものがいかに偽りに満ち、いかに誤った判断でゆがめられているかは、あきれ返るほどである。
戦いは、大軍を投入して短期間に勝を決せよ。
危険を伴わずに、偉大なことは何も成し遂げられなかった。
運命の女神は、積極果敢な行動をとる人間に味方する。
謙譲の美徳を持ってすれば、相手の尊大さに勝てると信ずるものは、誤りを犯すはめに陥る。
人は大局の判断を迫られた場合は誤りを犯しやすいが、個々のこととなると意外と正確な判断をくだすものである。
必要に迫られた際に大胆で果敢であることは、思慮に富むことと同じといってよい。
新秩序の導入は難しい。
これによって利益を失う者は必死で抵抗し、利益を得るものは消極的だからである。
地位獲得の当初は敵に見えた者のほうが、もともと味方であったものよりも役に立つことが多い。
人間が行動する動機には、敬愛と恐怖の二つがある。
しかし敬愛を重視しすぎると部下に軽蔑され、行き過ぎた恐怖で支配すると部下の心に憎悪を生む。
軍備は何よりも優先される。
突然に地位なり何なりを受け継ぐことになってしまったものにとって、心すべき最大のことは、何よりもまず最初に、しかも直ちに、土台を固めることである。
長期にわたって支配下に置かれ、その下で生きるのに慣れてしまった人民は、何かの偶然で転がり込んできた自由を手にしても、それを活用することができない。
裏切り者を裏切るのは二重の喜びだ。
人間は憎しみだけでなく、恐怖に駆られても相手に危害を加えようとする。
怒り狂った民衆に平静さを取り戻させる唯一の方法は、尊敬を受け、肉体的にも衆に優れた人物が、彼らの前に姿を現すことである。
相手をどんなことにしろ絶望に追い込むようなことは、思慮ある人のやることではない。
二人の優秀な指揮官より、一人の凡庸な指揮官のほうが、よほど有益である。
人生の砂時計から砂が落ちるほどに、そこを通してよりはっきりと見えるようになる。
ある君主の賢明さを評価するに際して一番の方法は、その人物がどのような人間を周りに置いているかを見ることである。
善行は悪行と同じように、人の憎悪を招くものである。
長所は必ず、短所を伴う。
人間というものは、自分自身の持ち物と名誉さえ奪われなければ、意外と不満なく生きてきたのである。
愛され、恐れられよ。
両方は無理なら、恐れられるのが望ましい。
君主にとっての敵は、内と外の双方にある。
これらの敵から身を守るのは、準備怠りない防衛力と友好関係である。
人間というものは、危害を加えられると思い込んでいた相手から親切にされたり恩恵を施されたりすると、そうでない人からの場合よりずっと恩に感ずるものである。
戦争とは、君主の唯一の研究課題である。
君主は平和を息継ぎの時間、軍事上の計画を立案して、実行に移す能力を身につける暇を与える時間とみなさなければならない。
ライオンは策略の罠から身を守れないし、キツネはオオカミから身を守ることができない。
人間ならば、策略の罠を知り尽くすキツネのようであれ。
またオオカミを威嚇するライオンでもあれ。
われわれが常に心しておかねばならないことは、どうすればより実害が少なくて済むかということである。
名将と凡将との差は、作戦能力の優劣よりも、責任観念の強弱によることが多い。
自らの地位の存亡に関わらない悪評でも、可能な限りそれを避けうるほどに賢明である必要がある。
もっとも、それが不可能であれば、あまり気にすることなくそのままにしておいてよい。
民衆は、群れを成せば大胆な行為に出るが、個人となれば臆病である。
国家の指導者たる者は、必要に迫られてやむを得ず行ったことでも、自ら進んで選択した結果であるかのように思わせることが重要である。
人間というものは、わが身のことになればおのれを甘やかし、たやすく騙されてしまう。
持続的な成功を求める者はだれであれ、時代に合わせて行動を変えなければならない。
衆に優れた人物は、運に恵まれようと見放されようと、常に態度を変えないものである。
人はささいな侮辱には復讐しようとするが、強力な攻撃には復讐する気が失せる。
人は心中に巣食う嫉妬心によって、誉めるよりもけなすほうを好むものである。
人間というものは、必要に迫られなければ善を行わないようにできている。
誰かが助け起こしてくれるのを期待してわざと倒れても、誰も助けはしない。
新しい秩序を打ち立てるということくらい、難しい事業はない。
なぜ、人々の心に自由に生きることへの強い愛着が生まれてくるのか、という問いへの答えは簡単である。
歴史上、自由を持つ国だけが領土を拡張し経済的にも豊かになったからである。
良い進言から君主の深い思慮が生まれるのではなく、君主の深い思慮から良い進言が生まれるのである。
わたしは現状維持には興味がない。
ひっくり返したいのだ。
民衆への対処の仕方は、寛大な態度でのぞむか、それとも強圧的に対するかのどちらかでなくてはならない。
大衆の判断は、抽象的に説明されたときに間違う。
中ぐらいの勝利で満足するものは、常に勝者であり続けるだろう。
君主は、自らの権威を傷つける恐れのある妥協は、絶対にすべきではない。
君主は人を二種類に分けて考え、それに応じた接し方をすべきである。
それは手放すことが出来ない人物か、そうでない人物かである。
傭兵に守られている国というのは、敵国から攻撃を受けない間だけ命を永らえているに過ぎない。